この記事に辿り着いたあなたなら「クリティカルシンキングとは何か?」あるいは「クリティカルシンキングの鍛え方を知りたい」と考えていることだろう。
このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。
クリティカルシンキングとは「物事を鵜呑みにせずに吟味し、適切に疑う思考態度」のことを指す。別名「批判的思考」とも呼ばれる。
「批判的」と聞くと何やら物騒な感じがするが「クリティカルシンキング(批判的思考)」はこれからのビジネスパーソンにとって必要不可欠な考え方だと断言できる。
なぜなら、今後ビジネスパーソンに求められるのは「決まったことを正確にできる人」ではなく「常識を疑い、自分の頭で考え、新しい価値を生み出せる人」だからだ。そのカギを握るのがクリティカルシンキングといえる。
よって、今回は「クリティカルシンキング」のポイントや鍛え方を、例題も交えながら解説する。その内容は以下の通りだ。
- クリティカルシンキングとは何か?
- クリティカルシンキングに必須の2つの実践ポイントとは?
- クリティカルシンキングの鍛え方の具体手順とは?
情報や知識は「目に見えるもの」だ。そして短時間で簡単に手に入る。しかし短時間で得られる競争力は、短時間で真似される競争力でしかない。
一方で「クリティカルシンキング」などの「思考力」は「目に見えないもの」であり、いったん身につければ、簡単には真似できない長期的な競争力になる。ぜひ今回の解説を、あなたの「持続可能な競争力」に結び付けて欲しい。
また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ活用頂きたい。
- ★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる
- クリティカルシンキングとは何か?
- クリティカルシンキングのポイントと例題
- クリティカルシンキングの鍛え方と例題
- クリティカルシンキングの本|おすすめ書籍2冊
- このブログから書籍化した本4冊
- その他の解説記事とおすすめ書籍
- 終わりに
- クリティカルシンキングとは|批判的思考のポイントと鍛え方|スライド資料
★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。
さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。
KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。
コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。
短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。
「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。
そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。
「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。
「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。
本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。
クリティカルシンキングとは何か?
クリティカルシンキングとは?-1:わかりやすい意味
クリティカルシンキングの「クリティカル(critical)」とは「批判的」という意味を持つ。このことから、クリティカルシンキングは別名「批判的思考」とも呼ばれる。
「批判」といえば、日常用語では悪いニュアンスが伴うが、本来の「批判」の定義とは「良い部分・悪い部分を意識的に見分け、評価・判定すること」であり「先入観にとらわれず、中立的な姿勢を重視する」という意味だ。
これらを踏まえると、クリティカルシンキングのわかりやすい定義は下記のようになる。
物事を鵜呑みにせず適切に疑うことができれば、これまでの当たり前や常識を覆し、新たな側面の発見につながる。
- 自分の考えは正しいはず
- 専門家が言ってることは正しいはず
- みんなが頷いているから正しいはず
- 論理的に筋が通っているのだから正しいはず
- 常識的に考えると正しいはず
そんな思い込みに対して適切に疑う態度を持ち「別の可能性はないか?」を考え続けるのがクリティカルシンキングだ。
クリティカルシンキングとは?-2:クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違い
ここで、クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違いについても触れておこう。
ロジカルシンキングとは、筋道立てて矛盾なく推論を行う思考法のことを指す。

しかしロジカルシンキングは「前提の置き方」を教えてはくれない。別の言い方をすれば「前提の置き方」次第で「結論」は無数に存在することになる。
また、ロジカルシンキングは論理を展開する際の「切り口(視点)」を教えてくれるわけではない。物事を考える際には多様な切り口が存在するが「切り口の選び方」に正解はない。

あらゆるビジネスが未来に向けてなされる以上、ビジネスの世界に「正解」など存在しない。
置いている前提が1ミリでも変われば、その後の未来は大きく変わる。そして、過去に成立した因果関係が未来にも成立するとは限らない。
だとすれば、ビジネスに絶対的な模範解答などなく、常に「暗中模索」や「試行錯誤」があるだけだ。
クリティカルシンキングをマスターしている人はそのことを理解しており、どんなに素晴らしい本に書いてあったことも、どんなに論理の筋道が通っていたとしても、全ては「こうかもしれない」という可能性の一つに過ぎないと考える。
そのため、時に誰もが驚くような「別の可能性」を見出して、周囲を驚かせることがあるのだ。
クリティカルシンキングのポイントと例題
続いては、ロジカルシンキングとの違いを意識しながら、クリティカルシンキングの実践ポイントを解説していこう。
クリティカルシンキングの実践ポイント-1:「前提」を批判的にを疑う
まずは下記の図をご覧いただきたい。もしあなたがロジカルシンキングをご存知なら、下の図が「ロジックツリー」であることは、すぐに気づくはずだ。

ロジカルシンキングの場合、まずは「売上を上げる」という前提を「受け入れる」。受け入れた上で、右側の箱に、
- 新規の購入者数を増やす
- 既存顧客の購入頻度を上げる
- 客単価を上げる
など「売上を上げるための手段」へと分解していく。

しかし、クリティカルシンキングでは「売上を上げる」という前提を「受け入れる」前に、まずは「建設的に前提を疑う」ことから始めるのがポイントだ。

あらゆる企業において「売上を上げる」ことは必要不可欠だ。しかし「売上を上げる」ことは「利益を上げる」ための手段であり目的ではない。
ビジネスの局面によっては「売上を上げる」より「コストを下げ、利益を増やす」ことのほうが重要な局面がある。
また、例えどんなに高い売上を上げたとしても、それ以上にコストがかかり利益がマイナス(つまり赤字)になってしまえば本末転倒であることは、あなたも理解できるはずだ。
だとすれば「売上を上げる」という前提をいったんは疑い「利益を上げる」ことを目的にすれば、その手段は「売上を上げる」だけでなく「コストを下げる」という別の選択肢も見えてくる。

このように、ロジカルシンキングは、
- 目的を「前提」として受け入れて
- その前提を元に論理の筋道を考えていく「思考技術」
であることがわかる。一方でクリティカルシンキングは、
- 「目的という前提」そのものを建設的に疑い
- 別の可能性を探そうとする「思考態度」
であるといえる。
クリティカルシンキングの実践ポイント-2:「切り口(視点)」を批判的に疑う
続いて、以下の図をご覧いただきたい。こちらも「ロジックツリー」の展開例だ。

もし「売上を上げる」場合、想定される手段は先ほど解説した通り、
- 新規の購入者数を増やす
- 既存顧客の購入頻度を上げる
- 客単価を上げる
のいずれかとなる。そしてこれらは、
- MECE(モレなくダブリなく)が成立している
- 「売上を上げる」という目的に対する手段として、因果関係が成立している
という2つを満たしてることから「ロジカルシンキング的には」全く問題のないロジックツリーだ。
しかしあなたがクリティカルシンキングを身につけたいなら、適切に疑う思考態度を持たなければならない。例えば「分解の切り口は、本当に正しいのか?」という疑い方だ。

確かに売上を上げるためには、
- 新規の購入者数を増やす
- 既存顧客の購入頻度を上げる
- 客単価を上げる
のどれかを実現しなければならない。
しかしこれらはすべて「企業側から見た視点」であり「市場側から見た視点」が入っていない。
だとすれば「市場から見た視点」を取り入れ、以下のような切り口で分解するのはどうだろうか?

売上高を「市場規模×市場シェア」という切り口で分解すれば、
- 売上を上げるために、市場を広げていくべきなのか?
- 売上を上げるために、市場シェアを上げるべきなのか?
という「市場」を加味した「戦略レベルの検討」ができるようになる。もし市場が成長局面なら「市場を広げる」という成長戦略が優先課題となるかもしれない。
あるいは市場が成熟局面なら「競合ブランドからのブランドスイッチを促す」という競争戦略が優先課題となりうる。

鋭いあなたならお気づきの通り「論理の筋道が正しい(=ロジカルシンキング的視点)」ことと「論理の筋道を考える際の切り口が正しい(=クリティカルシンキング的視点)」こととは、まったく別次元の問題だ。
「論理的に正しい」ことと「ビジネス的に正しい」ことは、必ずしもイコールにならない。
だからこそ「論理的に正しいからOK」ではなく「本当にその切り口(=論点)で正しいのか?」を疑い続ける思考態度が必要となる。それがクリティカルシンキングのポイントだ。
クリティカルシンキングの鍛え方と例題
クリティカルシンキングとは何か?が理解できたら、続いては「クリティカルシンキングの実践ポイント」について具体例を交えて解説していこう。
クリティカルシンキングの鍛え方と例題-1:適切に疑う「視点」を持つ
この記事をお読みのあなたなら、すでに「ロジカルシンキングとは何か?」について理解していることだろう。
ロジカルシンキングの本を読めば、必ずといっていいほど登場するのが「So What?/Why So?」のフレームワークだ。
「So What?」とは「だから何?」という意味合いであり「現在持っている情報から、主張や結論を導き出す際の問いかけ」だ。

また「Why So?」とは「なぜ、そう言えるのか?」という意味合いであり「結論に対して、納得できる理由があるかを確認する問いかけ」と言える。

しかし賢明なあなたならお気づきだと思うが「So What?/Why So?」は「原因と結果」や「根拠と結論」など、物事の因果関係を検証するためのフレームワークであり「前提を疑う視点」や「多様な切り口(=イシュー)を見出す視点」が入らない。そのため、現状を覆し、別の可能性を切り拓くのには向いていないのが難点だ。
もしあなたがクリティカルシンキングを実践したいなら「So What?/Why So?」以外に持っておきたいのが、以下の2つの視点だ。
- True?-本当か?
- Anything else?-他には?

適切に疑う視点を持つ-1:True?(本当か?)
クリティカルシンキングに必要な視点の1つ目は「True?(本当か?)」という視点だ。
ビジネス環境が目まぐるしく変化している現在では「今までの方法でうまくいったのだから、これからもこの方法でうまくいくはずだ」といった考え方は通用しない。
例えば、これまで小売業界では「整然とした商品陳列と売れ筋把握」が成功要因とされてきたが、その常識を「True?(本当か?)」と問いかけたのがドン・キホーテだ。
ドン・キホーテは「魔境感のある商品陳列」と「本当に売れるの?と思えるような見せ筋の仕入れ」という常識を覆すアプローチで売上を伸ばしており、ビジネス 前提を疑うことで成功している事例だ。
このように、これまでの「当たり前」や「常識」を「True?(本当か?)」と疑うことができれば、様々な可能性に思考を巡らせることができる。
適切に疑う視点を持つ-2:Anything else?(他には?)
クリティカルシンキングに必要な視点の2つ目は「Anything else?(他には?)」という視点だ。
例えば以下の通りだ。
- タイの高級洋菓子市場は市場規模が拡大している。
→高級洋菓子市場が拡大しているのはタイだけなのか?その他の国はないのか?
→高級洋菓子市場以外は拡大していないのか?例えばカジュアルギフト市場はどうか? - 自社にとって「タイの高級洋菓子市場」は魅力的な市場だ。
→市場が拡大しているだけで「魅力的」といえるのか?
→市場の成長性だけでなく、市場規模は十分か?
→競争環境は激しくないのか?
→自社の強みは活かせるのか?
このように、現在の視点に対して「Anything else?(他には?)」という視点を持てれば、より広い視野で、かつ精緻に物事を捉えることができるようになる。その結果、より確度の高い意思決定へとつながるはずだ。
クリティカルシンキングの鍛え方と例題-2:適切に疑う「思考習慣」を持つ
続いて、クリティカルシンキングの鍛え方を、問題解決プロセスに準じて解説しよう。
適切に疑う思考習慣を持つ-1:現状を疑う
冒頭で、クリティカルシンキングとは「物事を鵜呑みにせずに吟味し、適切に疑う思考態度」だと解説したが、クリティカルシンキングを実践する習慣を持てれば、これまで当たり前すぎて誰も気づかなかった問題に気づけるようになる。
なぜなら、問題発見は「現状の在り方」や「現状の方法」を疑うことから始まるからだ。
そして当たり前のことだが、そもそも問題を発見できなければ、問題を解決することはできない。

上記を踏まえれば、本質的な問題を発見し解決するには、クリティカルシンキングが必須のスキルであることがご理解いただけるはずだ。
もしあなたがクリティカルシンキングを鍛えたいなら、まずは現状を適切に疑う(True?)ことから始めよう。
そうすれば「時代に合わなくなった常識」「不合理なルール」が認識できるようになり、問題解決のスタートラインに立てるようになるはずだ。
適切に疑う思考習慣を持つ-2:問題を疑う
現状を疑い問題が発見できたら、次は「問題を疑う」ステップだ。より分かりやすく理解するために、具体例を交えて解説しよう。
もしあなたが、テーマパークの責任者だったと仮定しよう。
そのテーマパークは驚くほどの盛況で、毎日のように開門ゲート前に行列ができる状況だ。
責任者であるあなたにとっては嬉しい限りだが、一方でゲート付近は極端に狭い作りのスペースになっているため、ゲートが開いて群衆が一斉に走り出した際に、互いの肩がぶつかりあうような状況だ。
つまり、いつ事故が起きてもおかしくない状況といえる。
あなたは責任者として現場担当者に改善策を検討させたところ、以下のような提案が挙がってきた。
- 問題:ゲート付近が極端に狭い作りになっていること
- 解決策:ゲート付近に工事を入れ、人同士がぶつからないようにスペースを広げる
この問題解決策は、問題を「ゲート付近が極端に狭いスペースになっていること」と定義している。
しかしクリティカルシンキングとは「物事を鵜呑みにせずに吟味し、適切に疑う思考態度」のことだ。よって責任者であるあなたは、本当に「ゲート付近が極端に狭いスペースになっていること」が問題なのか?(=True?)と疑わなければならない。
そして、もし問題そのものを適切に疑うことができれば、
- 真の問題は「ゲート付近が極端に狭い作りになっていること」ではなく「入場者が一斉に走り出してしまうこと」だ。
という新たな気づきを得ることができる。
そうすれば、入場者が一斉に走り出さないように「入場直前に、テーマパーク内で使えるクーポン冊子を配る」という別の解決策を導き出すことも可能になる。
入場者がクーポン冊子を手に取れば、走りながら文字は読めないため急ぐ人を減らすことができるからだ。

このように「問題」は「問題そのものを疑い、捉え直す」ことで、解決が容易になる場合がある。
上記の例の場合「ゲート付近に工事を入れること」と「入場直前にクーポン冊子を配ること」では、後者の方がはるかに手間がかからず、低コストで問題を解決できるはずだ。
もしあなたがクリティカルシンキングを鍛えたいなら、問題を発見した際には「その問題の捉え方は、本当に正しいのか?」と適切に疑う(True?)習慣をつけよう。そしてうまく問題を捉え直すことができれば、驚くほど簡単に問題解決に至る場合がある。
適切に疑う思考習慣を持つ-3:思考の偏りに気づく
問題の解決策を考える際に、多くの人が陥りがちなのが心理バイアスだ。
「バイアス」とは「偏り」のことであり、人が人である以上「価値観」や「性格」も含めて「心理的な偏り」は避けようがない。
しかし、あらかじめ「人はどのような心理に偏りやすいのか?」を知っておけば、常に「この考えはバイアスがかかっていないか?」と疑えるようになりバイアスを避けやすくなる。
特に、多くの人が陥りやすい心理バイアスは以下の通りだ。
- 現状維持バイアス:
変化を避け、現状を維持したくなる心理バイアス - リスク回避性向:
得られる利益の大きさより、失う損失の大きさを重視してしまう心理バイアス - バンドワゴン効果:
みんなが良いと評価しているものを高く評価してしまう心理バイアス - ハロー効果:
目立ちやすい特徴に引っ張られ評価してしまう心理バイアス - フレーミング効果:
知らないうちに視点や枠組みを固定してしまう心理バイアス

心理バイアスが恐ろしいのは、多くの人がこれらのバイアスに対して無自覚であることだ。つまり、疑うきっかけや余地がないまま、無意識に受け入れてしまっているともいえる。
いったん疑いはじめれば「何を疑うべきか」は自然と見えてくることが多いが、そもそもバイアスに無自覚で「疑う気がない」あるいは「疑うということを思いつかない」ときには、疑う思考回路自体が働かなくなる。
もしあなたがクリティカルシンキングを鍛えたいなら、様々な心理バイアスに自覚的になり、常に「自分は心理バイアスに囚われていないか?」と疑う習慣を持ち続けよう。
適切な思考習慣を持つ-4:別の可能性を考え続ける
問題解決策を立案する際には、自分に対して常に「True?」と問いかけることで前提を疑い「Anything else?」と問いかけることで別の可能性を模索しつづけよう。
例えば、以下のロジックツリーをご覧になってほしい。法人営業における一般的なロジックツリーだ。

ここまでお読みのあなたなら「このロジックツリーを鵜呑みにしない」のがクリティカルシンキングであることはご理解いただけているはずだ。
仮に「売上を上げるには?」という前提が正しいとした場合、分解の切り口には、どのような「別の可能性」が考えられるだろうか?
例えば、以下のロジックツリーは「売上は営業が上げるもの」という前提を疑い(=True?)、それ以外のどんな可能性がありうるか?(=Anything else?)というクリティカルシンキングの視点で作成したロジックツリーだ。

もし広報活動で商品カテゴリー自体の社会的ニーズを創造することができれば、それは市場が広がることを意味するため、売上向上につながりやすくなる。
またマーケティング活動では、ブランドマーケティングによって商品の知名度が上がれば、それだけ引き合いの数は多くなり、売上向上につながりやすくなる。
また、コンテンツマーケティングを通して資料請求数が増えれば、こちらも売上向上に寄与していくはずだ。
これらのように「売上を上げるのは営業だけ」「改善すべきは営業活動プロセスだけ」と考えるのではなく、常に「前提は正しか?(=True?)」「他にはないか?(=Anything else?)」と考え続ける習慣を鍛えることができれば、あなたはすでに立派なクリティカルシンカーだ。
クリティカルシンキングの本|おすすめ書籍2冊
締めくくりに、あなたにおすすめできる「クリティカルシンキング本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。
- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるクリティカルシンキング本。
- 実際に実務や事例共有に役立っているクリティカルシンキング関連書籍。
- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せるクリティカルシンキング本。
もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。
クリティカルシンキング本おすすめ書籍-1:ビジネス思考法使いこなしブック
ロジカルシンキング・ラテラルシンキング・クリティカルシンキングという3つの思考法を体系的に扱っている書籍は、そう多くはない。そのような中で、それぞれの思考法の違いも含めて、わかりやすくかつ体系的に学べるのが本書の特徴だ。
本書では3つのキャラクターが登場し、同じ問題に対してそれぞれのキャラクターがロジカルシンキング・ラテラルシンキング・クリティカルシンキングの異なるアプローチで問題解決策を立案する。その際に「どのように結論が変わりえるか?」という比較がなされるため、それぞれの思考法の違いが理解しやすいのが特徴だ。
また、表紙の画像をご覧いただければわかる通り、内容はとっつきやすく物語形式で描かれているため「クリティカルシンキングとは何か?」「クリティカルシンキングはロジカルシンキングと何が違うのか?」と迷いがちな初心者にはわかりやすいはずだ。
もしあなたが「クリティカルシンキングは難しそう」と感じるなら、初めのとっかかりとしてふさわしい書籍だ。
クリティカルシンキング本おすすめ書籍-2:入社1年目で知っておきたい クリティカルシンキングの教科書
あなたは「論理的思考は理解できるが、なかなか実践できない」と悩んではいないだろうか?
例え論理的思考の方法論が理解できたとしても、誰にも認識されていない課題を自ら設定できなかれば、主体的な行動を起こすことはできない。そして「誰にも認識されていない課題」を設定する上で必要不可欠なのがクリティカルシンキングだ。
本書は、主体的な課題設定ができる「クリティカルシンカー」になるために必要な「実践のプロセス」や「重要ポイント」をステップごとに提供してくれている。
もしあなたがクリティカルシンキングを「実践」に落とし込みたいなら、ぜひ手元に置いておきたい書籍だ。
このブログから書籍化した本4冊
★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。
なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。
しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、
- 「センスが必要」
- 「経験の積み重ねが物を言う」
など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。
しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。
おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。
さらにAmazonレビューでも、
- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」
- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」
- 「一生もののスキルになるのは間違いない」
など有難い言葉を頂戴している。
もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。
★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。
一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。
PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。
このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。
ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、
- そもそも、何について考えるべきなのか?
- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?
などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。
本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。
本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。
★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」
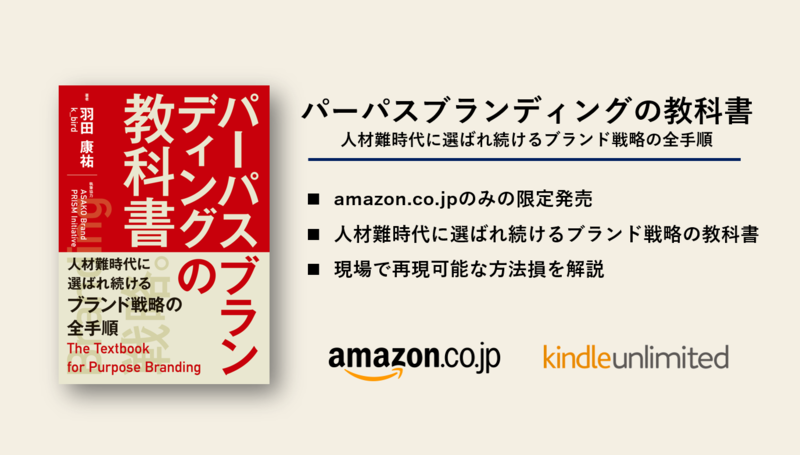
「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。
あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?
人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。
本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。
そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。
「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。
本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。
- パーパスブランディングとは何か?
- 今なぜパーパスブランディングなのか?
- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク
- ビジュアルアイデンティティ
- インナーブランディング
- パーパス採用ブランディング
- ESG・サステナビリティ統合
- アウターブランディング
もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。
「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。
そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。
ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。
本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。
本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。
「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。
本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。
おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、
- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」
- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」
- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」
など、ありがたい言葉を頂いている。
- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。
- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。
- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。
もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、
- なぜ、そうなのか?
- どう、ビジネスに役立つのか?
- 何をすればいいのか?
を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
その他の解説記事とおすすめ書籍
おすすめ記事
★思考力が身につくおすすめ記事
★ビジネススキルが身につくおすすめ記事
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事
おすすめ書籍
★17のビジネス分野別おすすめ書籍
★思考力が身につくおすすめ書籍
★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍
終わりに
今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかる解説」を続けていくつもりだ。
しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。
それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。
k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。







