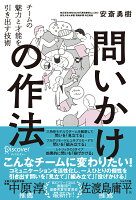このページに辿り着いたあなたなら、なんらかの理由で「マネジメントの本」や「管理職の本」を探していることだろう。
このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングファームと広告会社の両方のキャリアを持つ筆者が、ブランディングやマーケティング、ビジネスにおける「できない、わからない」の解決を目指しているブログだ。
筆者は外資コンサル時代及び広告会社時代を含め数百人越える管理職の方と仕事をしてきたが、人材育成やプロジェクトマネジメントに悩みをお持ちの方は非常に多い。
また筆者自身も、現在は広告会社の管理職として、日々試行錯誤を繰り返している。コンサルティングファームも広告会社も、極めて個性が強く多様な人材がチームを組んで仕事に当たる。そのため「チームマネジメントのスキル」は常に重要な関心ごととなる。
今回はそんな環境で働いてきた筆者がおすすめできる「マネジメント本」を紹介しよう。どれも本ブログの筆者であるk_birdが、日々「マネジメント」と格闘するなかで「ぜひ読むべき」という結論に至ったマネジメント本だ。
★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。
さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。
KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。
コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。
短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。
「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。
そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。
「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。
「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。
本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。
- ★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる
- マネジメント本おすすめ書籍-1:管理職として人材育成スキルを身につける本3冊
- マネジメント本おすすめ書籍-2:リーダーシップを身につける2冊
- マネジメント本おすすめ書籍-3:チームマネジメントのスキルを身につける4冊
- マネジメント本おすすめ書籍-4:プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトマネジメントスキルを身につける3冊
- マネジメント本おすすめ書籍-5:チームの生産性向上スキルを身につける4冊
- マネジメント本おすすめ書籍-6:会議の生産性向上スキルを身につける2冊
- マネジメント本おすすめ書籍-7:KPI&PDCAの本2冊
- マネジメント本おすすめ書籍-8:ドラッカーのマネジメント本1冊
- このブログから書籍化した本4冊
- その他のおすすめ書籍と解説記事
- 終わりに
それでは、ここからはおすすめマネジメント本を紹介していこう。1年で発刊されるビジネス書は、5,000冊を越えると言われる。しかし、その中で時代を越えて通用する書籍は、そう多くはない。そのような中で選定したマネジメント本は分野別に19冊となる。分類は以下の通りだ。
- 管理職として人材育成スキルを身につける本3冊
- リーダーシップを身につける本2冊
- チームマネジメントのスキルを身につける本4冊
- プロジェクトマネジメントスキルを身につける本3冊
- チームの生産性向上スキルを身につける本2冊
- 会議の生産性向上スキルを身につける本2冊
- KPI&PDCAを身につける2冊
- ドラッカーのマネジメント本1冊
さらに選定基準は、以下の基準のどれかに当てはまるものとした。
- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるマネジメントの良書。
- 実際に「思考の範囲を広げる」あるいは「知恵を見出す思考能力を鍛える」ことに役立っているマネジメント関連書籍。
- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せるマネジメント本。
- 主に管理職向けに書かれた、実践的なおすすめマネジメントスキル本
19冊と分量が多い理由は、本の読み方・活かし方|あなたをブランドにするおすすめ読書法でも解説している通り「分野ごとの固め読み」のメリットを重視しているからだ。
「分野ごとの固め読み」をすれば、同じ分野の書籍が主張する「共通点」と「差異点」が浮き彫りになる。そして「共通点」「差異点」それぞれに対して思考を巡らすことができれば、ビジネス読書は単なる「知識止まり」にならない。「あなたオリジナルの考え」を形創るきっかけとなるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-1:管理職として人材育成スキルを身につける本3冊
マネジメント本おすすめ書籍-1:
自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科書
突然の質問で恐縮だが、今あなたの目の前に「おなかをすかせた人」がいたら、あなたはどのような行動をとるだろうか?
- おなかをすかせているのだから、食料を与える
- 「食料の得かた」自体を教える
もしおなかをすかせた人が「餓死寸前」なら食料を与えることが先決だ。しかし上記を仕事に当てはめるなら「食料の得かたを教える」が部下育成の正解となる。
管理職の間からは「部下は指示待ちで、自分の頭で考えて動いてくれない」という不満をよく聞く。そして優秀な人であればあるほど率先垂範を行い、的確な指示を出し続ける。
しかし部下の側から見れば、上司が「率先垂範」し「的確に指示」すればするほど「答えは与えられるものだ」と感じるようになり「指示待ち状態」になっていく。
本書はそんな悪循環を断ち切り「答えを教える」のではなく「答えの出し方を考えさせる」方法や「その際の接し方」を解説した書籍だ。
もしあなたが「部下の指示待ち状態」で悩んでいるのなら、一読に値するおすすめの書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-2:
困った部下が最高の戦力に化けるすごい共感マネジメント
部下は、成果を出すための道具ではない。
当たり前のことだが、部下は「1人の人間」であり、1人の人間である以上、感情を持った生き物だ。
管理職であるあなたは、そんな部下に対してしっかりと「感謝の気持ち」を伝えているだろうか?部下の「可能性」を信じ、その「可能性」を伝えきれているだろうか?あなたが嬉しい時には嬉しい、悲しい時には悲しいと、率直な感情を伝えているだろうか?
ビジネスの世界では、ロジックが重要だとよく言われる。しかしあなたの部下は人間である以上、気持ちや感情もまた、業務のパフォーマンスに大きな影響を与えることは自明の理だ。
本書は、このような「部下の感情」に着目し「共感マネジメント」と称して「共感の力」で部下育成・チームマネジメントを実践していく方法論が記されている書籍だ。
リーダーの心がけ次第で、部下やチームは変わる。もしあなたが「指示・命令レベル」を越えて「感情レベル」で志を共有する部下を育成したいなら、本書は一読の価値があるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-3:
対話型マネジャー 部下のポテンシャルを引き出す最強育成術
本書は1on1ミーティングの第一人者である筆者が、上司と部下の対話に対して「具体的に何をどうやれば、部下の成長に寄与するのか?」を解説した書籍だ。
1on1ミーティングとは、部下の育成・モチベーションの向上を目的とした、上司と部下の対話の場だ。従来の「面談」と大きく異なるのは、その目的が主に「部下のために時間」に使われることだ。
今や1on1ミーティングは多くの組織に普及した感があるが、一方で「何を」話し「どう」話を深めていけばいいかがわからず、そのまま立ち消えになってしまうことも多い。
このような状況の中、本書はその処方箋として「9ボックス」というフレームワークを紹介し、1つ1つのボックスに対して、部下との対話を広げたり深めたりする実践的な方法が紹介されている。
また、対話例が豊富に紹介されていることから、具体的なイメージが掴みやすいのも秀逸だ。
もしあなたが「これから1on1ミーティングを取り入れてみたい」あるいは「1on1ミーティングを取り入れたものの、最近マンネリ気味になっている」という状態なら、ぜひ本書を手に取ってみて欲しい。
マネジメント本おすすめ書籍-2:リーダーシップを身につける2冊
マネジメント本おすすめ書籍-4:
最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと
ビジネスの成功には、チームリーダーや管理職の存在が重要であることは疑いようがない。
リーダーシップやマネジメントについては数多くの書籍が出版され、様々な定義がなされているが、本書はリーダーシップやマネジメントの「本質的な要素は何か?」を追求し、調査と科学の知見を踏まえながら核心部分を提示してくれている書籍だ。
特筆すべき点は、抽象論にとどまらず具体的にどういう行動を起こせばよいかまでを指南している点だ。
心の構え方次第で、見える景色は変わる。もしあなたがリーダーやマネージャーなどの管理職なら、あなたが見える景色を劇的に変えてくれるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-5:
WHYから始めよ! インスパイア型リーダーはここが違う
本書はTEDで4000万回以上再生された講演動画「How great leaders inspire action」から生まれた、リーダーシップのベストセラー書籍だ。
本書では、地位や権限で人を動かす「形式上のリーダー」ではなく、人々を感激させ奮起させる「本物のリーダー(オーセンティックリーダー)」の重要性を繰り返し説いている。
また「本物のリーダー」になるために必要なのは「WHAT(何を)」ではなく「WHY(なぜ)」であり、大義、理想、信条から物事を考える習慣として「ゴールデンサークル」というフレームワークを提示してくれている。
本書を読めば、リーダーシップとは「地位」や「権力」の発揮ではなく、人々が望む素晴らしい目標による「共感」「共鳴」を得て支持者を広げていくことであることがわかる。
チームメンバーは、リーダーが先頭に立つから付いてくるのではない。リーダーが掲げる社会的使命や価値観に共鳴し、チームメンバーが後押ししてくれるから、リーダーは先頭に立つことができる。
もしあなたが「WHYでインスパイアするリーダーシップ」を手に入れたいなら、本書は傍らに置いておきたい書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-3:チームマネジメントのスキルを身につける4冊
マネジメント本おすすめ書籍-6:
心理的安全性のつくりかた
あなたは「心理的安全性」という言葉をご存じだろうか?
「心理的安全性」とは、チーム全体の成果に向けて「率直な意見」「素朴な質問」「違和感の指摘」が、いつでも、誰もが気軽に言える状態を指す。
Googleが4年間の歳月をかけた「プロジェクト・アリストテレス」で、チームパフォーマンスに決め手になる重要な要素として、一躍有名になった考え方でもある。
本書は、この「心理的安全性」に対して、理論と体系に裏付けられた実践方法を指南している書籍だ。
この本が優れている点は、心理的安全性に関係する要素を「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新規歓迎」という4つの要素に分けることで、具体的なマネジメント行動に落としやすくしている点だ。
また、心理的安全性が高いチームを作るには、現状を変える「変革」が必要になるが、本書が「変革の3段階」を解説してくれている点も秀逸だ。
もしあなたが「指示待ち状態のチーム」を、心理的安全性が高い「創造的なチーム」へと変えていきたいなら、本書は必読だ。
マネジメント本おすすめ書籍-7:
問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術
人は誰しも「思考の限界」が「行動の限界」をつくる。そして「行動の限界」は、そのまま「成果の限界」をつくってしまう。
もし「思考の限界」「行動の限界」「成果の限界」を突破したいなら、チームメンバーの力を借り、チームメンバーの魅力と才能を引き出す「問いかけの技術」を手に入れることだ。
本書は、学習環境デザインという領域で認知科学的な実証研究を繰り返してきた筆者が「問いかけの技術」についてまとめた書籍だ。
本書の秀逸な点は、
- 当たり前に囚われて、そのまま自動的に受け入れてしまいがちになる「認識の自動化」
- 社会的役割が「相手に対するわかったつもり」を生み出してしまう「関係性の固定化」
- 「はみ出すこと」を恐れることによる「衝動の枯渇」
- タスクを分解することにより手段が目的化する「目的の形骸化」
という「チームの現代病」に対して、理論に裏打ちされた実践的な処方箋を提供してくれていることだ。
正しい答えは、間違った「問いかけ」からは生まれない。そして「正しい答え」を越えて、多様な可能性を「創って」行きたいなら、チームメンバーに投げかける「問いかけの技術」は必要不可欠だ。
もし「問いかけの技術」をマスターしたいなら、本書は良きガイド本となるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-8:
できるリーダーは、「これ」しかやらない メンバーが自ら動き出す「任せ方」のコツ
もしかしたらあなたは、適切なマネジメントを行いたくても十分な時間が取れないことに困ってはいないだろうか?
本書は、仕事を部下に任せることで自分の時間を浮かし、適切なマネジメントを実践していくための方法を、7章60項目に分けて解説した書籍だ。
特に本書が秀逸なのは「部下への仕事の任せ方」に留まることなく「部下が自ら動く組織の作り方」が分かりやすく紹介されている点だ。
マネジメントとはいかにうまく仕事を任せられるかであり、それが自分の成長のため、部下の成長ため、そしてチームの成長のためになる。
もしあなたがチームを成長させるためにも、適切な「任せ方」を身につけたいなら、本書は大きな助けになるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-9:
たった1分で相手をやる気にさせる話術ペップトーク
あなたは「ペップトーク」をご存じだろうか?
ペップトークとは、シンプルに定義すれば「人やチームを励ますメソッド」のことだ。もともとはスポーツの世界で使われていたメソッドだが、アメリカではビジネス界でも頻繁に使われている。
本書は、そんな「ペップトーク」の実践法を解説した書籍だ。ペップトークの方法論は、大きく以下の4つで構成されている。
- 事実を正確に認識し、受け入れていることを示す
- 事実に対する捉え方をポジティブに変える
- 行動の先にある未来を示す
- 必ず実現できることを信じさせ、励ます
本書で描かれているのは、物事は前向きに捉え、心に響く言葉を投げかけ、感情を鼓舞するための方法論だ。
もし、あなたがチームの士気に火をつけたいと思うなら、ぜひ身につけておきたいスキルだ。
マネジメント本おすすめ書籍-4:プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトマネジメントスキルを身につける3冊
マネジメント本おすすめ書籍-10:
担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメント」実践講座
ビジネスで成果を生むには、多くの関係者の協力が必要不可欠だ。
あなたの企業でも、様々な部門を横断するプロジェクト型の業務は多いはずだ。
本書は、プロジェクトマネジメントの初心者向けに、基本となる知識と技術を紹介した書籍だ。
本書の著者は、多数のプロジェクト現場の実行支援を経験しており「プロジェクト憲章」や「WBS」など、普段なら聞きなれないプロジェクトマネジメント用語なども丁寧に解説してくれている。
もし、あなたが初めてプロジェクトマネージャーを経験することになったのなら、本書はプロジェクトのイロハを理解する上で、おすすめ書籍となる。
マネジメント本おすすめ書籍-11:
プロジェクトリーダーの教科書
本書は、アクセンチュア・PwC・IBMで13年間に渡りプロジェクトのトラブルリカバリーに従事してきたコンサルタントが執筆した書籍だ。
本書が秀逸な点は「プロジェクト=必ず問題が起こるもの」と捉え、プロジェクトの12のステップごとに、プロジェクトリーダーに必要なマインドセットやスキルセット、アクションを解説してくれている点だ。
プロジェクトとは、極論すれば人と人との営みである以上、極めて泥臭い取り組みだ。しかし本書はそこから逃げず、具体的かつ実践的なノウハウがまとめられている。
もしあなたが本書を一読すれば「プロジェクトのどこに落とし穴があって」「どのような心構えで対峙すればスムースに進むのか?」が手に取るようにわかるはずだ。
マネジメント本おすすめ書籍-12:
抵抗勢力との向き合い方
プロジェクトといえば、つい目的やゴール、あるいはタスクなど「プロジェクトの中身」に目が向きがちだ。
しかし、プロジェクトを成功に導くためには、もう一つ重要な要素が存在する。それは「プロジェクトの機運」だ。
プロジェクトに関わった人のモチベーションが高く、かつ組織が一体となって使命感に燃えているようであればプロジェクトの成功確率は高くなるが、一方で「他人事」「様子見」あるいは「抵抗」が生じると、プロジェクトの機運は急速に失速する。
本書は、プロジェクト失速の原因となる「抵抗勢力」に焦点をあて「いかに抵抗勢力と向き合うか?」を解説した書籍だ。
本書は「プロジェクトの局面ごとによく現れる抵抗の例」「まずい対処の仕方」「良い対処の仕方」などを、体系的に、かつ実例を交えて解説している。
実は、抵抗する側にも、理屈はある。
そんな理屈をあらかじめ知っておけば、あなたはプロジェクトの機運を失速させるリスクを事前につむことができるはずだ。
もしあなたがプロジェクトマネジメントに対して「中身のマネジメント」だけでなく「機運のマネジメント」も適切に行いたいなら、本書は必読だ。
マネジメント本おすすめ書籍-5:チームの生産性向上スキルを身につける4冊
マネジメント本おすすめ書籍-13:
生産性―マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの
あなたは「生産性」と聞いて、どのようなことを思い浮かべるだろうか?
「コストの削減」や「会議・作業時間の削減」が思い浮かんだとしたら、ぜひこの本を読んでほしい。間違いなく、あなたにとって「目からウロコ」のはずだ。
こと生産性において、つい日本人は「何かを削減すること」をイメージしがちだ。しかし生産性を上げるためには「時間やコストの削減」だけでなく「価値の向上」という側面も存在する。
本書は、前述した「採用基準」と同様に、マッキンゼーの人材育成・採用マネージャーとして参画した17年間に裏打ちされたモノの見方だ。
筆者は数々の新人コンサルタントと接しており「生産性を下げるポイント」も「生産性を上げるポイント」も熟知している。
日本企業は、押しなべて生産性が低いといわれるが、あなたのチームの生産性はいかがだろうか?
マネジメント本おすすめ書籍-14:
外資系コンサルの知的生産術 プロだけが知る「99の心得」
「ロジカルシンキング」「ラテラルシンキング」「デザイン思考」…。あなたがどれだけ多くの「思考法」を手に入れたとしても、それだけではあなたのチームの生産性は上がらない。
なぜなら「生産性」とは「思考」だけでなく「行動」を伴って初めて実現するからだ。
本書が優れている点は「ビジネスパーソンとして圧倒的に質の高いクオリティを素早く出すにはどうすれば良いのか?」について「思考法」だけでなく「意志決定の視点」や「行動」にまで落とし込まれている点だ。
通常の書籍であれば「読んで学ぶ」という姿勢になりがちだが、本書の場合「読みながら使う」という姿勢が適切だ。
チームメンバーに論理思考やフレームワークを学ばせても、なかなか仕事がはかどらない。そうお感じの方にこそ、お勧めしたい書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-6:会議の生産性向上スキルを身につける2冊
マネジメント本おすすめ書籍-15:世界で一番やさしい会議の教科書
もしあなたがマネージャーなら「生産性の低い会議」を「生産性の高い会議」に変えたいと思っていることだろう。
世の中には、数多くの「会議本」が溢れている。
そしてその多くは「会議の目的を明確にしよう」「会議の終了時にはToDoを明確しよう」などと解説されていることが多い。
しかしあなたは実際の会議の現場で、いきなり「会議の目的はなんですか?」「今後のToDoはなんですか?」などと、ズケズケと聞けるだろうか?
本書は「物語+解説」という形式をとり、入社2年目の若手社員が小さなことから改善を積み上げ、少しずつ会議を変えていく様子が「物語」と「解説」の両面で描かれている。そのため、日々の会議の「現場感」を失わない形で「会議を変えていく手法」が理解できるのが特徴だ。
更に本書は「会議の進行役側」の視点でなく「会議の参加者側の視点」に立って「隠れファシリテーター」としてより良い会議に変えていく手法やコツが解説されている点も秀逸だ。
会議は、例えあなたが参加者側だったとしても、変えることができる。
もしあなたが生産性の高い会議を実現するために「実践可能な」方法論を手に入れたいなら、本書は必読に値する書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-16:世界で一番やさしい会議の教科書 実践編
本書は、上記「世界で一番やさしい会議の教科書」の実践編となる書籍だ。
「世界で一番やさしい会議の教科書」は「物語形式による現場感」が重視されているため、会議ファシリテーションの手法ついて網羅的に解説されているわけではない。
一方で本書は「続編」として会議ファシリテーションを体系的に整理し、前著では説明しきれなかった現実的な技法を「8つの基本動作」として解説している。
また、会議ファシリテーションは多くの参加者を巻き込む以上、組織的に定着させていくことが有効となるが「組織に定着させる方法論」についても「定着の4段階サイクルと浸透の6パターン」に整理して解説している。
本書は、数多くある会議ファシリテーションの書籍の中でも、リアルな現実と向き合った「泥臭い」書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-7:KPI&PDCAの本2冊
マネジメント本おすすめ書籍-17:最高の結果を出すKPIマネジメント
本書は、リクルートの出身者である著者が「リクルート流のKPIマネジメントの方法論」をわかりやすく解き明かしている書籍だ。
著者の中尾氏は、リクルート社員として新規事業の立ち上げやKPIマネジメントを実践してきた経験を持つ。さらには、11年間にわたりリクルートグループ内の勉強会で「KPI」や「数字の読み方」の社内教師をしてきた経歴の持ち主でもある。
そんな著者が描いた本書は、いわば「リクルート流KPIマネジメント」の理論と実践の両方が詰め込まれた書籍といえるだろう。
もしあなたが「KPI設定」を学びたいなら一番初めに手に取りたい書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-18:xDrive 質問でPDCAは加速する
これは当たり前のことだが、チームのPDCAは、自分一人だけでは回せない。
あなたがどんなにPDCAの知識やスキルを身につけても、他のチームメンバーに主体性や当事者意識がなければ、チーム全体でのPDCAは回らない。
本書は、そんなチームメンバー達に「質問」を通して思考を促しながら、当事者意識を作ることでPDCAを回す方法を解説した書籍だ。
本書が秀逸なのは、単なる「考え方」にとどまらず、チームメンバーのPDCAを回すための120個もの「質問集」が用意されており、極めて実践的なのもありがたい。
もし、チームメンバーの当事者意識がPDCAのボトルネックになっているなら、本書はその解決策になる書籍だ。
マネジメント本おすすめ書籍-8:ドラッカーのマネジメント本1冊
マネジメント本おすすめ書籍-19:
マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則
世の中には2種類の異なるタイプの情報が流通している。その2種類とは「フローの情報」と「ストックの情報」だ。
「フローの情報」とは流れ去る情報のことで、いわば「タイムライン」のようなイメージだ。一方で「ストックの情報」とは、あなたが思考を巡らすことで「あなたならでは知恵」に発展可能な情報を指す。
「フローの情報」の価値は「新しいこと」だが「ストックの情報」の価値は「時代を越えて変わらない本質・原理」が潜んでいることだ。
そして自分の中に「変わらない本質・原理」が蓄積されていけば、いざというときに様々な要素を「変わらない本質・原理」に当てはめてみることで、質の高い解が素早く導き出せるようになる。これが「本質」や「原理」の効果だ。
本書は、経営学の神様といわれるピーター・F・ドラッカー が「マネジメントの本質・原理」を体系化した過去の著作のエッセンス版であり、本書を読めば一通り「ドラッカー」が理解できるはずだ。
約60年前の記述が今なおベストセラーで在り続けているのは、時代を越えても変わらない重要な本質・原理が描かれているからだろう。
テクニックは、決して本質や原理を越えることはない。もしあなたがマネジメントに携わるなら、その「本質」や「原理」を理解する上で、読んでおきたい一冊だ。
このブログから書籍化した本4冊
★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。
なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。
しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、
- 「センスが必要」
- 「経験の積み重ねが物を言う」
など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。
しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。
おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。
さらにAmazonレビューでも、
- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」
- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」
- 「一生もののスキルになるのは間違いない」
など有難い言葉を頂戴している。
もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。
★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。
一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。
PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。
このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。
ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、
- そもそも、何について考えるべきなのか?
- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?
などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。
本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。
本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。
★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」
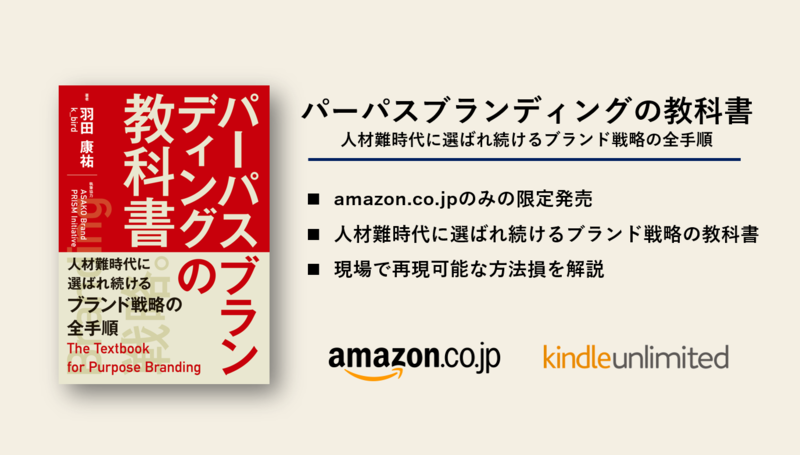
「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。
あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?
人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。
本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。
そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。
「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。
本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。
- パーパスブランディングとは何か?
- 今なぜパーパスブランディングなのか?
- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク
- ビジュアルアイデンティティ
- インナーブランディング
- パーパス採用ブランディング
- ESG・サステナビリティ統合
- アウターブランディング
もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。
「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。
そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。
ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。
本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。
本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。
「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。
本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。
おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、
- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」
- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」
- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」
など、ありがたい言葉を頂いている。
- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。
- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。
- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。
もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、
- なぜ、そうなのか?
- どう、ビジネスに役立つのか?
- 何をすればいいのか?
を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
その他のおすすめ書籍と解説記事
おすすめ書籍
★17のビジネス分野別おすすめ書籍
★思考力が身につくおすすめ書籍
★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍
おすすめ記事
★思考力が身につくおすすめ記事
★ビジネススキルが身につくおすすめ記事
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事
終わりに
今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかる解説」を続けていくつもりだ。
しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。
それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。
k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。