
このページに辿り着いたあなたなら「ブランディングの定義とは?」あるいは「ブランディングの種類」など、ブランディングの基礎知識に関心があることだろう。
このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ブランディングやマーケティングの「できない、わからない」を解決するブログだ。
ブランディングは抽象的な概念であるため、人によって複数の「ブランディングの定義」が乱立してしまい、混乱をきたしてしまう例が後を絶たない。
よって、今回は「ブランディングの定義」そして「ブランディングの3つの種類」についての解説を行う。その内容は以下の通りだ。
- ブランディングとは何か?実務に落としやすい「ブランディングの定義」とは?
- ブランディングの3つの種類とは?
もしこの解説を最後まで読んでいただければ、あなたは一通り「ブランディングとは何か?」そして「ブランディングの種類」についての知識が身につくはずだ。
★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。
「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。
そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。
ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。
本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。
本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。
「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。
本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。
おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、
- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」
- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」
- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」
など、ありがたい言葉を頂いている。
- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。
- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。
- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。
もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、
- なぜ、そうなのか?
- どう、ビジネスに役立つのか?
- 何をすればいいのか?
を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
- ★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」
- ブランディングとは?ブランディングの定義
- ブランディングの3つの種類
- ブランディングを理解する:おすすめブランディング本3冊
- このブログから書籍化した本4冊
- その他の解説記事とおすすめ書籍
- 終わりに
ブランディングとは?ブランディングの定義
ブランディングとは何か?実務家に役立つブランディングの意味
ブランディングには様々な定義が乱立しているが、このブログの筆者であるk_birdは以下のように定義している。
- ブランディングとは、そのブランドならではの独自の役割を築き「できるだけ多くの人に」「できるだけ強い」感情移入を形創っていく取り組みを指す。
- その成果は「指名買い」によるロングセラーブランドだ。
ブランディングとは「できるだけ多くの人に」「できるだけ際立った」独自性と感情移入を形創っていく活動を指す。その成果は「指名買い」によるロングセラーブランドだ。
どのような製品・サービスも、独自の役割を築き、感情移入を促す取り組みを続けることによって、長く愛されるブランドに変わる。つまり「指名買いされるロングセラーブランド」に育てることができる。
このことは「製品」「商品」「ブランド」の違いを理解すれば、より明確になる。
製品とは?
「製品」とは、工場の倉庫にある出荷待ちのものを指す。
製品開発者が長年かけて開発し、工場担当者が丹精込めて生産する。倉庫担当者が倉庫棚に整理し、出荷待ちの状態となる。しかしこの時点で生活者の関与はなく、企業側主導で事が進められる。

商品とは?
「商品」とは、お店の棚に並んだ販売待ちのものを指す。
商品開発担当者が「どう売るか?」を考えながらロゴやパッケージデザインを開発し、価格設定もなされている。
そして営業担当者が「どうバイヤーと交渉し、棚に並べてもらうか?」を考え、知恵を搾る。そしてその努力が結実すれば、無事小売店の棚に並ぶことになる。
しかし、商品棚には様々な競合商品がひしめきあっている。
そしてたまたま偶然その棚を通りがかった生活者が、たまたま偶然あなたの商品を目にし、たまたま偶然その時のニーズにマッチすれば、買い物かごに放り込む。
「商品」の状態のままでは、数々の「たまたま偶然」をくぐり抜けた上での「衝動買い」に頼らざるを得ない状況だ。
結果「衝動買い」を創るために、販売促進担当者が「どう売るか?」を考え、値引き販売をしてみたり、ノベルティを付けてみたり、懸賞キャンペーンを展開するなど、やはり「製品」と同様、企業側主導で事が進められることが多いはずだ。
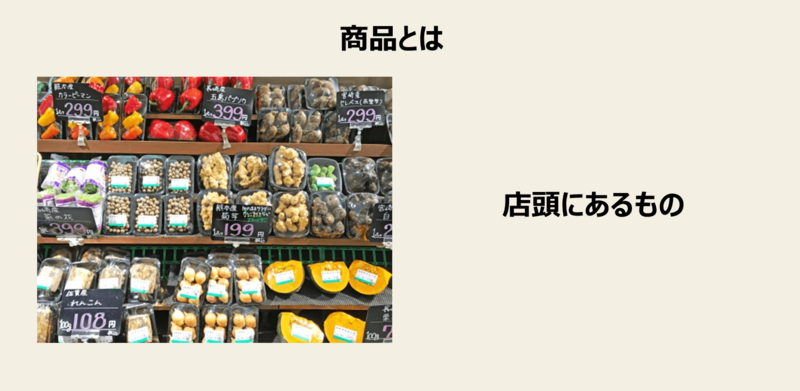
ブランドとは?
「ブランド」とは、生活者1人1人の心の中にある。
長年、広告代理店と外資系コンサルティングファームの両方で「ブランディングのリアル」を体験してきたk_birdにとって、実務に直結しやすい「ブランドの定義」は以下の通りシンプルだ。
ここでぜひ、強いブランド力を持つと評判のブランドを思い起こしてみて欲しい。
アップル、グーグル、ディズニー、スターバックス、コカ・コーラ…。どのブランドも独自の役割を築き、単なる「モノ」や「サービス」を越えて、生活者からの感情移入が伴っていないだろうか?
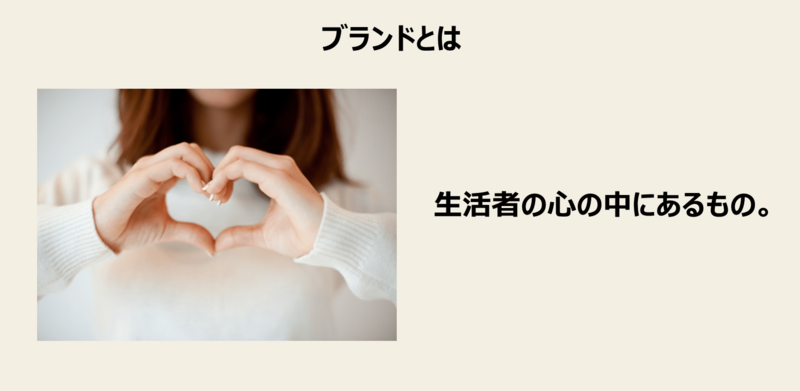
このブログの筆者であるk_birdは、広告代理店と外資系コンサルティングファーム時代を合わせて、延べ300回以上のマーケティングリサーチ経験を有している。
その経験からしても、独自の役割を築き、感情移入が伴っているブランドとそうでないブランドでは、指名購入意向率が5倍以上違う例はザラにある。一方で、逆の例は1件も見たことがない。
どのようなモノやサービスも、人が感情移入した時、その人にとっての「ブランド」に変わる。

ブランディングの3つの種類
「ブランディングとは何か?」が理解できたら、続いては「ブランディングの種類」について解説しよう。ブランディングは、大きく分けて3つの種類が存在する。
- 「何を」ブランディングするのか?:
「商品・サービスブランディング」と「企業ブランディング」 - 「誰に」ブランディングするのか?:
「アウターブランディング」と「インナーブランディング」 - 「誰が」ブランディングするのか?:
「BtoCブランディング」と「BtoBブランディング」

以下、わかりやすく解説しよう。
ブランディングの3つの種類-1:商品・サービスブランディングと企業ブランディング
「何を」ブランディングするのか?を基準に分類すると、ブランディングは「商品/サービスブランディング」と「企業ブランディング」の2種類が存在する。

商品/サービスブランディングとは、その名の通り商品/サービス単位でブランディングを展開することを指す。
一般的には「ターゲット=商品/サービスの見込み客」であり、マーケティング領域でのブランディングであることから、別名ブランドマーケティングとも呼ばれる。
日本では「ブランディング」といえば「広告宣伝」という手法論に矮小化されがちだが、欧米ではブランディングはマーケティングの上位概念の戦略として位置付けられている。欧米企業がブランディングに長けており、マーケティングを「ブランドマーケティング」と呼ぶのはこのためだ。
一方で企業ブランディングとは、個々の商品ではなく、企業単位でブランディングを展開することを指す。企業ブランディングの対象は「社会」「従業員」「取引先」「株主・投資家」など「全ステークホルダー」となるのが一般的だ。
近年の企業ブランディングの例では、松下電器がパナソニックへ、 富士重工がスバルへと企業名を変更し、企業ブランディングを展開したのは記憶に新しいところだ。
ブランディングの3つの種類-2:アウターブランディングとインナーブランディング
「誰に向けて」ブランディングするのか?を基準に分類すると、ブランディングは「アウターブランディング」と「インナーブランディング」の2種類に分けることができる。

アウターブランディングとは、消費者や顧客など自社の「外側」にいる人達に対してブランディングを展開することを指す。
一方でインナーブランディングとは、別名「インターナルブランディング」とも呼ばれ「従業員」を中心に、自社の「内側」にいる人たちに対してブランディングを展開することだ。
インナーブランディングの目的は、従業員に対してブランドのミッション(社会的使命)やブランドビジョン(在りたい姿)あるいはブランドバリュー(価値観・マインドセット)を一人ひとりに理解してもらい、自分ごととして日々の業務を実践してもらうことだ。
スターバックスや東京ディズニーリゾートの例を見ればわかるように、人を介してサービスを提供するサービス業では、接客スタッフ1人ひとりの接客態度や接客品質がブランドの評価に直結していく。
また、近年「ブランド体験」や「カスタマージャーニー」の重要性が叫ばれて久しいが、部門を越えて一貫したブランド体験やカスタマージャーニーを実現していく上でも、インナーブランディングはとりわけ重要な取り組みとなる。
ブランディングの3つの種類-3:BtoCブランディングとBtoBブランディング
「誰が」ブランディングするのか?を基準に分類すると、ブランディングは「BtoCブランディング」と「BtoBブランディング」の2種類が存在する。

消費財を提供しているBtoC企業がブランディングすることを「BtoCブランディング」と呼ぶ一方で、ビジネス財を提供しているBtoB企業がブランディングを展開することを「BtoBブランディング」と呼ぶ。
グローバルなBtoB企業では、ブランディングに力を入れている企業は多い。例を挙げれば、IBM/GE/インテル/シスコシステムズ/オラクル/SAP/JPモルガン/アクセンチュア/アドビシステムズ/キャタピラーなど、数え上げればきりがない。
これらのBtoB企業は、世界のブランド価値ランキングの常連企業だ。そして高い収益性を実現していることからも分かる通り、ブランディングはBtoB企業にとっても大きな競争力となる。
ブランディングを理解する:おすすめブランディング本3冊
締めくくりに、マーケティング・ブランディング担当者へのお薦めのブランディング本を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。
- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるブランディング関連本。
- 実際に「ブランディング」の戦略&施策実務に役立っているブランディング関連本。
- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せるブランディング関連本。
もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。
ブランド論 無形の差別化を作る20の基本原則
ブランディングに携わる実務家にとって、デビッド・アーカーは避けて通れないはずだ。
いわゆる「アーカー本」には「ブランドエクイティ戦略」「ブランド優位の戦略」「ブランドポートフォリオ戦略」「ブランドリーダーシップ」の4冊が存在するが、その4冊のエッセンスを抜き出して、集大成として出版されたのが本書の「ブランド論」だ。
本書を読めば、ブランディング用語である「ブランドエクイティ」や「ブランドアイデンティティ」「ブランドパーソナリティ」など、ブランドに関わる理論やコンセプトが一通り学べるはずだ。
更に、これまでのアーカー本は「翻訳がわかりにくい」「価格が高い」などの欠点があったが、本書は他のアーカー本と比べれば価格も手ごろで、訳も読みやすくなっている。
ブランドに関わる実務家が、一通りアカデミックなブランド論を学ぶには最適な教科書だ。
ブランド戦略論
本書は、日本のブランド戦略論の第一人者が「ブランド理論」「ブランド戦略」「ブランド戦略の実践法」「事例」を包括的にまとめたブランド戦略の体系書だ。
本書の価格は4,400円と少々高いが、ブランド戦略の知識を集大成した百科事典のような本格的体系書であり、日本企業の事例掲載も8カテゴリー30社に昇る。よって、本書に一通り目を通せば、ブランド戦略の知識に困ることはないはずだ。
また「ブランド戦略の本格的体系書」と聞くと、ついアカデミックで読みずらいものを想像しがちだが、本書の著者は一流の学者でありつつも、ビジネスの最前線での実務経験も併せ持っていることから、極めて読みやすいのも秀逸だ。
もしあなたが腰を据えてブランド戦略を理解したいなら、まとまった時間を作って読んでおきたい一冊だ。
このブログから書籍化した本4冊
★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」
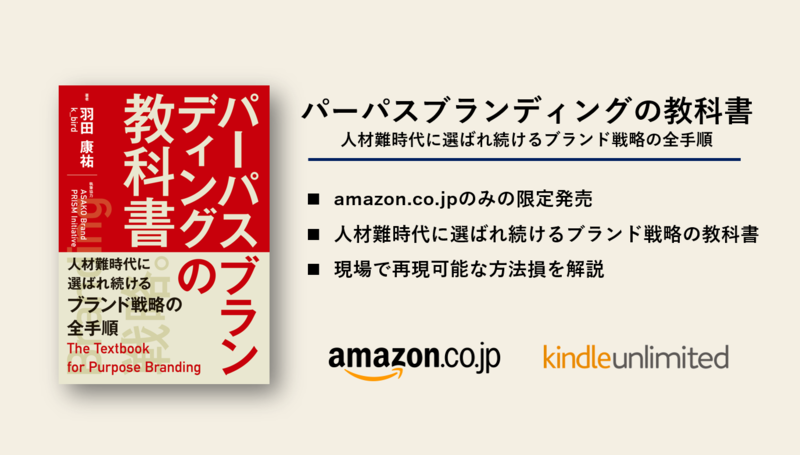
「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。
あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?
人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。
本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。
本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。
そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。
「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。
本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。
- パーパスブランディングとは何か?
- 今なぜパーパスブランディングなのか?
- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク
- ビジュアルアイデンティティ
- インナーブランディング
- パーパス採用ブランディング
- ESG・サステナビリティ統合
- アウターブランディング
もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。
また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。
★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。
さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。
KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。
コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。
短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。
「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。
そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。
「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。
「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。
本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。
★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。
なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。
しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、
- 「センスが必要」
- 「経験の積み重ねが物を言う」
など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。
しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。
おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。
さらにAmazonレビューでも、
- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」
- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」
- 「一生もののスキルになるのは間違いない」
など有難い言葉を頂戴している。
もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。
★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。
一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。
PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。
このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。
ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、
- そもそも、何について考えるべきなのか?
- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?
などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。
本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。
本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。
その他の解説記事とおすすめ書籍
おすすめ記事
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事
★思考力が身につくおすすめ記事
★ビジネススキルが身につくおすすめ記事
おすすめ書籍
★17のビジネス分野別おすすめ書籍
★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍
★思考力が身につくおすすめ書籍
★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍
終わりに
今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかるブランディングの解説」を続けていくつもりだ。
しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。
それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。
k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。






